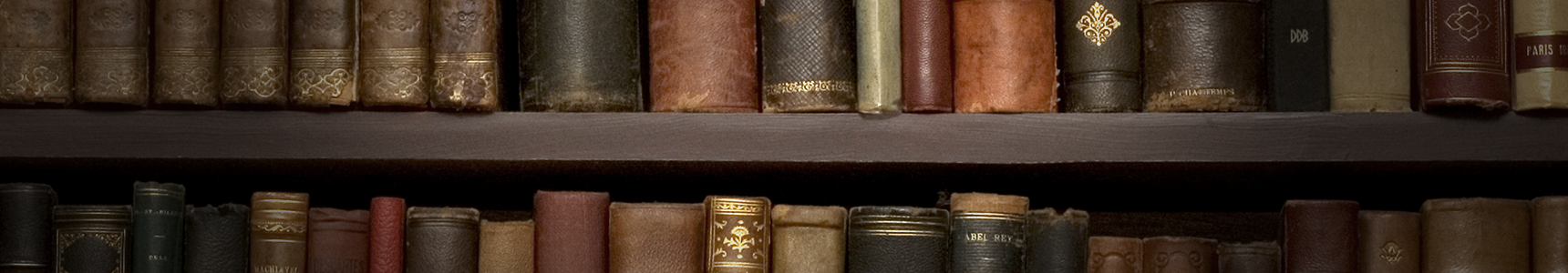
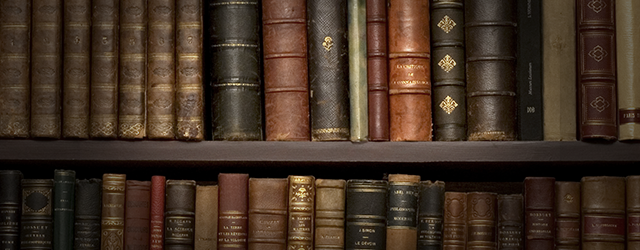
景品表示法を含む広告・表示規制等対応相談
① 景品表示法
企業が一般消費者向けのマーケティング活動を行う際には、様々な広告・表示規制を遵守する必要があります。特に、景品表示法については、例年40件前後の措置命令(行政処分)が行われており、当該命令の公表や報道等により、対象商品・サービスや企業自身にとって脅威が生じるおそれがあり、特に対応の必要性が高いといえます。
当事務所では、これまで広告・表示に関する多くのレビューや助言を行うとともに、消費者庁等による景品表示法の調査事件について数多く関与するなど、広告・表示規制に関し多数の対応経験を有しています。また、消費生活のデジタル化等の影響を受け、ステルスマーケティング規制が導入され、主観的No.1表示に関する実態調査報告書が公表される等、景品表示法は動きの激しい分野ですが、執行動向含め、それらの動きを適時に把握し知見を深めています。
広告・表示案に関する相談には、限られた時間で対応する必要のあるものが多く、また従前議論されていない問題の検討が必要となることもありますが、上記経験や知見を土台としたうえで、個別事例に応じた最良の方針を検討し、助言やサポートを行います。表示案について問題がある場合、例えば注釈の表示方法や表示内容に問題がある場合に強調表示部分から代替策を検討する等、知恵を絞り代替案を提供できるよう努めています。また、景品表示法においては、違反行為をしないよう、必要な体制の整備その他の「必要な措置」を講じることが義務付けられており、必要な措置は取扱商品・サービスや表示方法等により異なり得るものですが、当該措置に関するコンサルティングも行っています。
上記に関連する書籍として、『エッセンス景品表示法』(商事法務、2018年)、『景品表示法の法律相談〔改訂版〕』(青林書院、2018年〔共著〕)、『実務担当者のための景表法ガイドマップ』(商事法務、2024年)を執筆しています。また、当事務所の弁護士は、消費者庁の開催した「景品表示法検討会」の委員や、東京都のインターネット広告調査に係る助言員チーム「東京デジタルCATS」のメンバーを務めるなどもしています。
なお、当事務所では、アドバイザーとして、公正取引委員会の前事務総長であり、同委員会経済取引局長及び審査局長のほか、消費者庁審議官や経済産業省商務情報局消費経済対策課長等を歴任した小林 渉が在籍しており、弁護士とともに多角的な視点での最適な問題解決を目指しています。
② 景品表示法以外の広告・表示規制
広告・表示を行う際には、景品表示法以外にも、対象商品等に応じ、様々な規制等を意識する必要があります。
例えば、健康食品を含む食品を対象とする場合は(医薬品としての承認を得ていなくても)薬機法や健康増進法等を意識する必要がありますし、加工食品等の容器包装には食品表示法・食品表示基準に基づき表示を行う必要があります。特定保健用食品や機能性表示食品に関しては、各制度に関する理解も必要です。br> また、医薬品・医薬部外品・化粧品や医療機器の広告に際しては薬機法や医薬品等適正広告基準等を検討する必要があり、医療機関に関する広告表示を行う場合には医療法を意識する必要があります。さらに、通信販売を行う場合には特商法の広告規制や最終確認画面規制への対応を行う必要があります。他にも様々な広告・表示規制が存在し、いずれについても、関連する多くの行政文書・ガイドラインを踏まえた横断的な検討が必要です。
更に、不正競争防止法の品質等誤認惹起行為該当性や、独占禁止法の欺まん的顧客誘引該当性が問題になる場面もあります。
当事務所では、総合事務所として様々な業態の依頼者から多様なご相談を受けており、広告・表示規制に関して幅広く対応を行う中で、上記のような問題に関する知見も日々深めています。また、上記に関連する書籍として、例えば『ヘルスケア事業の法律実務』(中央経済社、2023年)を執筆するほか、機能性表示食品を含む食品に関する表示を対象とするセミナーを実施するなどしています。
③ 景品規制
マーケティング活動に際しキャンペーン等を行う際には、景品表示法の景品規制も遵守する必要があります。当事務所では、広告・表示に関する相談とともに多数の景品規制に関する相談も対応しており、特にポイント制度や複数事業者の関わるキャンペーン施策等、複雑な事案への対応を強みとしています。景品規制との関係でも、代替案の提供等、事案に即した助言やサポートを行っています。
景品表示法を含む広告・表示規制等対応相談を担当する弁護士
景品表示法を含む広告・表示規制等対応相談に関する他の執筆情報一覧を見る
- 2026.02.12
- 特許権・実用新案権と表示規制に関する一整理
- 2025.08.20
- 事業分野別に見るM&Aの勘所[第10回]Eコマース
- 2025.07.15
- 【連載】企業法務のための特商法講座(第5回)電話勧誘販売――アップセル・クロスセル等
- 2025.07.14
- ビジネスを促進する 景表法の道標 ~事例から読み説き導き出す解~
- 2025.06.01
- 景品表示法の法律相談〔第3版〕
- 2025.04.18
- 広告で「No.1」と表示してよい? 景品表示法上の留意点とは
- 2025.04.15
- 【連載】企業法務のための特商法講座(第2回)Eコマースに関する規制概観と最新動向(2)
- 2025.03.15
- 【新連載】企業法務のための特商法講座(第1回)Eコマースに関する規制概観と最新動向(1)
- 2024.10.28
- 越境ECの法規制は?アメリカ・EUの消費者保護法リスクを中心に
- 2024.10.17
- 景品表示法に関する2023年・2024年(9月まで)の動向概観
- 2024.10.01
- 景品表示法が規制する優良誤認表示とは?要件や違反事例を解説
- 2024.09.01
- 海外進出する企業のための法務 消費者問題
- 2024.07.02
- 実務担当者のための景表法ガイドマップ
- 2024.03.11
- 【連載】今さら聞けない景品表示法60ー当選本数の表示ー
- 2024.02.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法59ー12月公表の機能性表示食品関連措置命令ー
- 2024.01.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法58ー福袋と景品表示法ー
- 2024.01.10
- 6.30措置命令を契機として、機能性表示食品の広告・表示について考える
- 2023.12.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法57ー東京都による執行と東京デジタルCATSー
- 2023.11.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法56ー電気料金表示に関する措置命令ー
- 2023.10.25
- 景表法コンプライアンスと令和5年景表法改正のポイント
- 2023.10.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法55ー景品規制に関する行政指導の検討ー
- 2023.10.01
- BtoCのネット広告をめぐる規制の動向と対応
- 2023.09.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法54ーリニューアルされた景品Q&Aー
- 2023.08.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法53ーエキストラバージンオリーブオイルの表示ー
- 2023.08.01
- デジタル化と景品表示法上の問題
- 2023.07.31
- アフィリエイト広告に関する景品表示法の考え方
- 2023.07.31
- ステルスマーケティングに関する法規制と実務対応ポイント
- 2023.07.15
- ステマ規制への対応を考える――仮想事例を通じて
- 2023.07.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法52ー2023年景品表示法改正ー
- 2023.07.03
- 導入されるステルスマーケティング規制の概要及び対応
- 2023.06.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法51ー仮の差止め申立て事例ー
- 2023.05.22
- 景品表示法とは?基礎をわかりやすく解説
- 2023.05.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法50ーNo.1表示や比較広告に関する執行動向ー
- 2023.04.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法49ーグリーンウオッシュと景品表示法ー
- 2023.03.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法48ー取引価額の整理ー
- 2023.02.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法47ーステマ禁止に向けた動向ー
- 2023.01.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法46ー痩身効果表示の問題点ー
- 2022.12.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法45ープレスリリースと景品表示法ー
- 2022.11.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法44ーファンタジースポーツと景品規制ー
- 2022.10.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法43ー果物(ジュース)の表示ー
- 2022.09.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法42ー改正管理措置指針の概観と対応ー
- 2022.08.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法41ー行政指導事案と景品規制の検討ー
- 2022.08.01
- BtoC Eコマース実務対応
- 2022.07.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法40ー事後チェック指針に基づく指導と対応ー
- 2022.06.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法39ー無料の就職支援サービスと景品表示法ー
- 2022.05.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法38ー認知症専門リハビリに関する不当表示ー
- 2022.04.15
- 景品表示法コンプライアンス
- 2022.04.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法37ー不実証広告規制と最高裁判決ー
- 2022.03.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法36ー事業者が講ずべき措置に関する動向ー
- 2022.02.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法35ー脱炭素社会と環境配慮表示ー
- 2022.01.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法34ー比較広告の難しさー
- 2021.12.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法33ーゲーム以外の「カード合わせ」ー
- 2021.11.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法32ー原産国の表示ー
- 2021.10.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法31ー二重価格表示実践編ー
- 2021.09.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法30ー前年度運用状況と行政指導ー
- 2021.08.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法29ー冷却ベルトと合理的根拠ー
- 2021.07.28
- 景品表示法に関する2020年度の動向概観
- 2021.07.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法28ー埼玉県による措置命令事例ー
- 2021.06.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法27ーダークパターンと景品表示法ー
- 2021.05.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第9回)Eコマースに関連する近時の立法動向概観・総括
- 2021.05.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法26ー料理に関する表示事例ー
- 2021.04.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第8回)サイト表示に関する留意点(2)
- 2021.04.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法25ー施行から5年ー
- 2021.03.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第7回)サイト表示に関する留意点(1)
- 2021.03.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法24ーひな人形セットの店頭価格ー
- 2021.02.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第6回)規約運用・変更上の留意点
- 2021.02.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法23ー「合格実績」の数え方ー
- 2021.01.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法23ー乾杯のグラスの中身は!?ー
- 2020.12.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第5回)規約作成上の留意点(5)
- 2020.12.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法21ーグレーゾーン解消制度と景品表示法ー
- 2020.11.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第4回)規約作成上の留意点(4)
- 2020.11.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法20ー将来の価格とは?ー
- 2020.10.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第3回)規約作成上の留意点(3)
- 2020.10.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法19ー商品名を記載しない商品広告?ー
- 2020.09.15
- 【連載】第7回表示規制(6)
- 2020.09.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第2回)規約作成上の留意点(2)
- 2020.09.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法18ーGo To トラベルキャンペーンー
- 2020.08.17
- 【連載】第6回表示規制(5)
- 2020.08.15
- 【連載】Eコマース実務対応(第1回)規約作成上の留意点(1)
- 2020.08.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法17ーその懸賞、本当に当たりますか?ー
- 2020.07.15
- 【連載】第5回表示規制(4)
- 2020.07.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法16ーコンプガチャと景品規制ー
- 2020.06.15
- 【連載】第4回表示規制(3)
- 2020.06.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法15ー何から値引きをしているの?ー
- 2020.05.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法14ー動画広告の打消し表示ー
- 2020.04.15
- 【連載】第3回表示規制(2)
- 2020.04.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法13ー癒しの温泉ー
- 2020.03.25
- アマゾンジャパンによる景表法の措置命令取消訴訟
- 2020.03.16
- 【連載】第2回表示規制(1)
- 2020.03.16
- 【連載】景品表示法を知る・学ぶー表示規制(1)ー
- 2020.03.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法12ー健康に役立つ?ー
- 2020.02.17
- 【連載】景品表示法を知る・学ぶー景表法の概要ー
- 2020.02.17
- 【連載】第1回景品表示法の概要
- 2020.02.12
- 【連載】今さら聞けない景品表示法11ーチョコレートの表示ー
- 2020.01.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法10ー新春キャンペーンー
- 2019.12.12
- 【連載】今さら聞けない景品表示法09ー今年の"繰り返し"を振り返るー
- 2019.11.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法08ー「ポイント」って景品?ー
- 2019.10.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法07ーキャッシュレス還元事業×景表法ー
- 2019.09.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法06ー実は例外がありますー
- 2019.08.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法05ーステマは何がいけないの?ー
- 2019.07.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法04ーステーキ風!?ー
- 2019.06.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法03ー表示の内容になっている?ー
- 2019.05.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法02ーNo.1はダメなのか!?ー
- 2019.04.10
- 【連載】今さら聞けない景品表示法01ーキャンペーンの繰り返しー
- 2019.03.20
- 【特集1】不当表示を防ぎ,効果的な宣伝を促進する 広告審査法務の実践
- 2018.11.16
- 消費者庁による景表法違反調査への対応
- 2018.10.01
- 景品表示法の実務対応ポイント
- 2018.09.01
- 表示に際しての「確認」に関する考察
- 2018.08.01
- 課徴金制度導入後2年間を経過した景品表示法の執行状況について
- 2018.03.24
- eスポーツ大会における賞金提供と景品規制
- 2018.03.19
- エッセンス景品表示法
- 2017.09.20
- 「打消し表示」に関する覚書(下)-「打消し表示に関する実態調査報告書」の概説
- 2017.09.01
- 「打消し表示」に関する覚書(上)-「打消し表示に関する実態調査報告書」の概説
- 2017.06.20
- 経済刑法
- 2017.05.15
- 景品表示法におけるコンプライアンス(管理措置指針の実務的活用に向けて)
- 2017.04.01
- 広告は消契法の「勧誘」に該当し得るか
- 2017.02.15
- 三菱・日産事例をどう伝えるか―経営陣に伝えるべき3つのポイント
- 2016.09.30
- New Surcharge System under the Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations
- 2016.08.20
- 詳説 景品表示法の課徴金制度
- 2016.08.01
- BUSINESS LAWYERS ウェブサイト(2016年8月~)
- 2016.06.23
- 28年4月スタート!景品表示法の課徴金制度--気を付けたい不当表示と実務での対応--
- 2016.02.20
- 実務解説 4月1日施行 景表法の課徴金制度─政令・府令・ガイドラインの大要
- 2015.06.20
- 逐条解説 平成26年11月改正 景品表示法 課徴金制度の解説
- 2015.05.12
- 景品表示法への課徴金制度の導入 ~ 一般消費者による自主的かつ合理的な選択への一層の確保等を目的として~ 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成26年法律第118号
- 2015.02.03
- 特集 改正景表法が求める表示等コンプライアンス「改正景品表示法における課徴金制度の解説」
- 2015.01.07
- [霞が関インフォ]景品表示法改正法の成立(課徴金制度の導入)
- 2014.12.19
- 景品表示法改正法の成立(課徴金制度の導入)
- 2014.12.15
- 景品表示法改正法の成立(課徴金制度の導入)
景品表示法を含む広告・表示規制等対応相談に関連するセミナー情報一覧を見る
- 2026.05.13
- ベーシック景品表示法
- 2026.01.29
- 令和7年度第5回健康食品表示規制研究会セミナー
- 2026.01.15
- 消費者向け広告表示規制アップデート
- 2025.11.13
- 【会場/Zoom/後日配信】Eコマース規制の最新動向と実務対応【アップデート版】
- 2025.11.04
- 【WEB配信】令和7年度「事業者向けコンプライアンス講習会」
- 2025.05.28
- 第57回全国新聞広告審査研究会
- 2025.05.16
- ベーシック景品表示法
- 2025.04.23
- 【オンラインセミナー:録画配信】事業分野別M&Aセミナーシリーズ 第10回:Eコマース
- 2025.04.22
- 【オンラインセミナー】事業分野別M&Aセミナーシリーズ 第10回:Eコマース
- 2025.03.19
- 小売電気・エネルギー業界のための景品表示法 対策基礎講座
- 2025.03.17
- 【WEB配信】消費者向け広告・勧誘に関するルールの基礎知識
- 2024.11.01
- 【WEB配信】令和6年度「事業者向けコンプライアンス講習会」
- 2024.09.12
- 【オンラインセミナー】海外進出する企業のための法務 第16回: 消費者問題への対応
- 2024.06.07
- ベーシック景品表示法
- 2024.02.16
- デジタル関連の消費者トラブル-ネット通販や通信契約等のトラブルへの対応について-
- 2024.02.08
- 【オンラインセミナー】基礎からわかる特定商取引法
- 2023.11.08
- 【Web配信】令和5年度後期 景品表示法実務講座
- 2023.11.01
- 【WEB配信】令和5年度「事業者向けコンプライアンス講習会」
- 2023.08.03
- 消費者庁による景表法違反調査への対応 〜初期対応から行政処分前後の対応まで〜
- 2023.07.04
- 社内でどう説明しますか? 令和5年景品表示法改正の影響と対応事項
- 2022.10.21
- 景品表示法管理措置指針の改正解説講座 - アフィリエイト広告を指針対象に追加 -
- 2022.07.14
- 【ライブ配信】事例に学ぶ!広告表示の注意点
- 2022.02.18
- 【会場及びWEBセミナー】二重価格表示に関する景品表示法解説講座
- 2021.03.30
- 【ライブ配信】二重価格表示に関する景表法講座
- 2020.12.02
- 【WEBセミナー】景品表示法実務講座~景品と表示の実務~事例を基に
- 2020.09.28
- 【WEBセミナー】120分で概観 BtoCのEコマースに関する規制と対応の基礎知識
- 2020.09.25
- 消費者関連部門職員が知っておきたい知識と情報ーインターネット通販を中心にー
- 2020.02.13
- 景品表示法に対する企業の実務対応
- 2020.01.29
- 広告・表示に関するトラブルー最近の法改正等を踏まえて(消費生活相談員研修)
- 2019.12.18
- 広告・表示に関するトラブルー最近の法改正等を踏まえて(消費生活相談員研修)
- 2019.12.06
- 栄養情報Catch upセミナー
- 2019.10.09
- 不当表示事例を通じて理解する 景表法(表示規制)に関する近時の動向と求められる対応
- 2019.10.04
- 民法改正・Eコマース約款等を踏まえた約款コンプライアンス講座
- 2019.09.26
- 最新事情を踏まえたビジネス法務の重要論点② 消費者保護に関する表示規制
- 2019.06.11
- 【好評開催】わが社の表示は大丈夫!? 実際の違反事例で「基礎から学ぶ景品表示法」
- 2019.05.29
- 食品表示・広告に関するセミナー景品表示法に関する法令・事例の解説〜具体事例を中⼼に〜
- 2019.03.15
- 景表法課徴金事件解説講座
- 2019.01.24
- 90分で確認! 日本、中国及びシンガポールにおけるeコマースコンプライアンス概要
- 2018.07.12
- わが社の表示は大丈夫!? 実際の違反事例で「基礎から学ぶ景品表示法」
- 2018.02.18
- シンポジウム「景品表示法の実現手法の多様性-独禁法の視点も含めて」
- 2018.02.16
- 競争法実務家養成コース
- 2017.09.06
- 平成29年度 消費者問題に関する企業職員セミナー
- 2017.08.08
- 景品規制解説講座
- 2017.02.17
- 競争法実務家養成コース 第4回 景品表示法に対する企業の実務対応
- 2017.02.07
- 景品規制解説講座
- 2016.12.01
- 平成28年度後期 景品表示法実務講座
- 2016.09.16
- 改正景品表示法における課徴金リスクと対応 ―立案担当者が施行後の動向を踏まえて解説―
- 2016.07.21
- 保険広告等における不当表示によるリスクと対応
- 2016.03.28
- 改正景品表示法における課徴金制度の導入について
- 2016.03.14
- 景品表示法への課徴金制度の導入について
- 2016.03.11
- 景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会
- 2016.03.07
- 景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会
- 2016.02.24
- 景品表示法の課徴金制度の概要
- 2016.02.16
- 景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会
- 2016.02.09
- 改正景品表示法に関する説明会
- 2014.12.17
- 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」の解説







